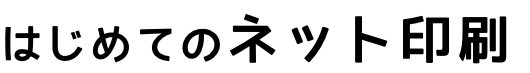ネット印刷とは?
印刷業界において最近耳にする「インターネット印刷」「ネット印刷」「ネットプリント」「印刷通販」といった言葉があります。簡単にいうと個人あるいは企業で印刷データを作って、ネットで注文・発注することです。インターネット時代の到来によって、ネット印刷も主流になってきました。
24時間いつでもネット上で注文・データ入稿・決済ができるだけでなく、日本全国、自分が希望の場所へ納期までに印刷物を届けてくれるという大変便利なサービスです。印刷価格が安いことが一番の特徴ですが、ネット注文だけにアウトプットのクオリティを疑う声もあります。
ネット印刷が誕生するまで
そもそもネット印刷はいつから誕生したのでしょうか?1990年代頃からマック(Mac)などのパソコンで印刷物の原稿データを制作できるようになりました。その頃は印刷するために必要な製版フィルムを作る「サービスビューロー」という業態が多く存在しました。そのサービスビューローがDTPによる印刷需要に応えていました。例えば、高価なPostScriptプリンタが買えないデザイナーが、校正確認用にカラーレーザー出力をサービスビューローに依頼したりしていたんですね。
このように1990年代後半になると、デザイナーや一般ユーザーがサービスビューローを利用するようになりました。データ出力が普通の時代に突入していきます。つまり「パソコンでデータを作成し、印刷物にする」ことを意味するDTP(DeskTop Publishing)が主流になりました。
パソコンで印刷データを制作するようになると、その印刷データをユーザーから郵送してもらって、製版から印刷・断裁・梱包までを請け負って、完成品をユーザーに宅急便で届ける(返送する)、というサービスが2000年前後に誕生しました。これがのちに「印刷通販」とよばれるものになります。
その頃から入稿形態も多様化していきます。データ記録媒体としてはMOディスクだけでなく、CD-R、DVDなどより大容量の記録媒体も用いられるようになりました。
そしてインターネットの普及によって郵送のやりとりではなく、オンライン上のやりとり、いわゆるオンライン入稿が誕生します。この流れから「インターネット印刷」と呼ぶのが正式名称だという意見もありますし、「印刷通販」の延長だという人もいますが、このサイトでは「ネット印刷」と呼ばせて頂きます。
どんな人が利用しているのか?
それでは今主流になっている「ネット印刷」ですが、どんな人が利用しているんでしょうか? それは「自分でデザインデータを用意することができる人や企業の担当者」になります。大きく分けるとすれば、「個人で使う場合」と「ビジネスとして利用する場合」という2つの方法になります。
個人で使う場合の例
・年賀状や暑中見舞いなどのはがき制作
・思い出に残るフォトブックの制作
・友人の結婚式での印刷物制作
・サークルや所属している会での印刷物制作
・特性カレンダーや名刺などを制作